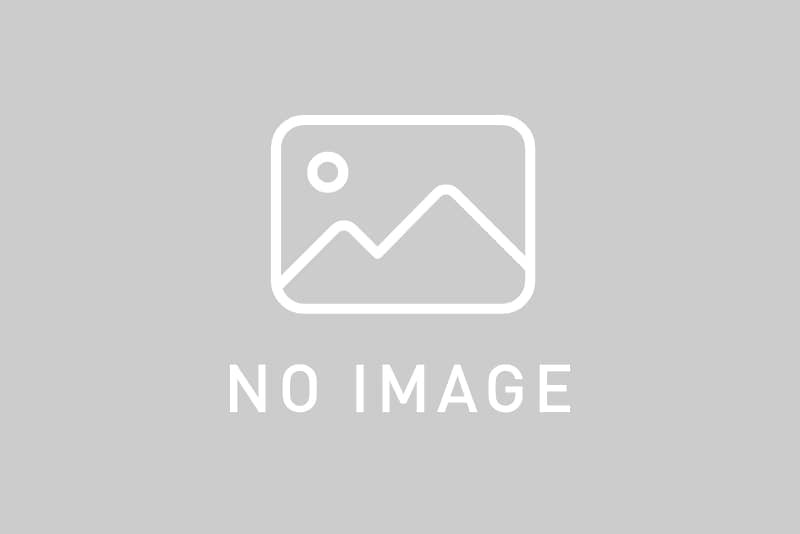イベント情報
令和7年度生涯学習講座 大阪大学せんばアカデミー「伊東信宏と聴く中欧の音楽」のご案内
- 受付中
- 開催終了
開催日時
2025年6月12日(木)から2026年3月12日(木)まで
文化・芸術
「文化芸能 ・ 国際交流」の拠点であり、大阪大学との連携企画が好評の《せんばアカデミー》。
2024年3月開通「箕面船場阪大前駅」すぐ、箕面船場の文化施設にぜひご来館ください。
2024年3月開通「箕面船場阪大前駅」すぐ、箕面船場の文化施設にぜひご来館ください。
【生涯学習講座・通期】大阪大学せんばアカデミー「伊東信宏と聴く中欧の音楽」
今年度の大阪大学せんばアカデミーでは、音楽学の伊東信宏教授をお迎えします。
「中欧の音楽」をテーマに、複数の作曲家に焦点をあて、独自の視点からクラシック音楽を読み解きます。
本講座では、CD を聴いたりDVDを見たりしながら、音楽の背景にある時代性や地域性を学びます。
伊東先生のお話しは、驚きにあふれ、あなたの好奇心を刺激することうけあいです。
案内チラシはこちら
| 講師 | 伊東 信宏(大阪大学人文学研究科教授/音楽学) |
|---|---|
| 日程 | 全10講座/各90分 2025年6月12日(木)から2026年3月12日(木)のうち10日間 |
| 定員 | 45名 |
| 主催等 | 主催:国立大学法人大阪大学(箕面市立船場生涯学習センター指定管理者) 運営:公益財団法人箕面市メイプル文化財団 |
受講料・お申込み
| 受講料 | ★全講座受講でお得になります★ 全10回通しの受講料:10,000円 ・全講座受講は、全回出席を原則とします。代理の方の受講はできません。 ・初回講座受付時に一括支払いとなります。一旦支払われた受講料は返金できませんのでご了承ください。1講座ずつの個別受講料:1講座につき1,600円 全講座受講の申込者で定員に達した場合、個別受講の申込みはございません。 |
|---|---|
| 申込締切 | 先着順 |
| お申込み | インターネット:https://minoh-bunka.com/kouza/ (外部リンク) ※申込フォームに必要事項を記入し締切日の午後5時までにご応募ください。 ※講座名の入力例: 全10回通しの場合 → 伊東信宏と聴く中欧の音楽・全講座受講 個別受講の場合 → 伊東信宏と聴く中欧の音楽①②(希望されるすべての講座番号をご入力ください)※郵送・窓口でのお申込みも可能です。インターネット以外のお申し込みはこちら。 |
| 問合わせ先会場 | 船場生涯学習センター 受付時間:9:00~17:00 Tel:072-730-5333 FAX:072-730-5349 住所:〒562-0035 箕面市船場東3-10-1 ※アクセス方法はこちら |
講座番号・講座名と日時
| 講座番号・講座名 【注意】第10回のみ時間と会場が異なります。 | 日時 | |
| 講座番号①「中欧の音楽(導入)」「中欧」とはオーストリア・ハンガリー・チェコ・スロヴァキア・ポーランドあたりのことを指すことが多いのですが、この地域は特に19世紀後半以降多くの作曲家、演奏家を生んできたところでもあります。初回は、本講座の全体を概観します。 | 6月12日(木) | 午前10時30分~正午 |
| 講座番号②「シューベルトの『美しき水車屋の娘』」シューベルトは生涯をウィーンの文化圏で過ごした作曲家で典型的な中欧の作曲家の一人でした。夏にはハンガリー貴族の家で音楽教師として過ごし、その経験は彼の音楽に「ハンガリー的」な痕跡を残しました。これらを辿りながらシューベルトの音楽について考えてみます。 | 7月10日(木) | |
| 講座番号③「シューベルトの『美しき水車屋の娘』(続き)」『美しき水車屋の娘』には、おぼろげな筋書きがあります。粉屋(=水車屋)で修行する若者が、その師匠の娘に惹かれ、やがて恋に敗れて自殺する、というものです。ここではこの歌曲集を、あまり思想的なものとしてではなく、もう少し通俗的な「サイコロジカル・ホラー」として読み解いてみたいと思います。 | 8月7日(木) | |
| 講座番号④「フランツ・リストと「ラプソディ」の音楽史」「ラプソディ」とは、音楽的には少し気まぐれな形式を持つ民族的色彩の濃い音楽ジャンルとして知られていますが、これはフランツ・リストの「ハンガリアン・ラプソディ」を始祖としています。リスト以来、様々な国、地域のラプソディが書かれてきました。ここではそのような「ラプソディ」の歴史を紐解きます。 | 8月28日(木) | |
| 講座番号⑤「中欧の作曲家としてのバルトーク」バルトークは20世紀前半の代表的作曲家の一人ですが、ハンガリーの民謡を研究しそれを基礎として新しい音楽を作り出そうとしたことで知られています。彼のルーツを辿りながら、その「中欧」的な性格を考えます。 | 10月9日(木) | |
| 講座番号⑥「バルトークと不定形な音楽」バルトークの「ラプソディ第2番」は、特にその終結部が何度も書き直されました。彼は、ルーマニアのロマによる荒々しい民俗音楽の素材をここに組み込もうとし、その扱いに手こずっていたのでした。晩年の『ルーマニア民俗音楽』という著作も含めて考えます。 | 11月13日(木) | |
| 講座番号⑦「中欧の作曲家としてのリゲティ」リゲティは1923年、ルーマニアに生まれたハンガリー語を母語とするユダヤ系作曲家で、ナチス・ドイツとスターリンのソ連による二つの全体主義を潜り抜けて、1960年代頃から西側の前衛音楽の第一線に躍り出たという経歴を持ちます。彼の音楽の「中欧」的性格を考えます。 | 12月11日(木) | |
| 講座番号⑧「作曲された悪夢(リゲティ)」ジェルジ・リゲティの出世作の一つ「アトモスフェール」(1961年)は、不協和で禍々しく、しかも濃密な響きを持つ管弦楽曲で、映画『2001年宇宙の旅』で使われたことでも知られています。これはリゲティが見たある「悪夢」から生まれた、とされていますが、果たしてどこまで信じてよいのでしょうか? | 1月8日(木) | |
| 講座番号⑨「クルターグの音楽」ジェルジ・クルターグはリゲティより3つ年下の存命の作曲家です。ルーマニア生まれのハンガリー語を母語とするユダヤ系作曲家という出自も似ており、実際に二人は親友でした。ですがリゲティとは対照的に、クルターグは内向的で寡作。そのような彼の音楽について考えます。 | 2月12日(木) | |
| ※講座番号⑩のみ、時間・会場が変更となります。 時間:午前10時30分~11時45分 会場:東京建物 Brillia HALL 箕面(文化芸能劇場) リハーサル室 講座番号⑩「クルターグの音楽(続き)」クルターグの『遊び』は、1970年代から書き始められ、現在10巻までが刊行されているピアノ小品集です。ほんの数音で終わってしまう曲、あるいはある音の周りの半音を一度に押さえるような指示、さらに長さを表す独特の記号など、個性的ですが深く沈潜する音楽です。実際に弾いたり、耳を澄ましたりして体験したいと思います。 | 3月12日(木) | |