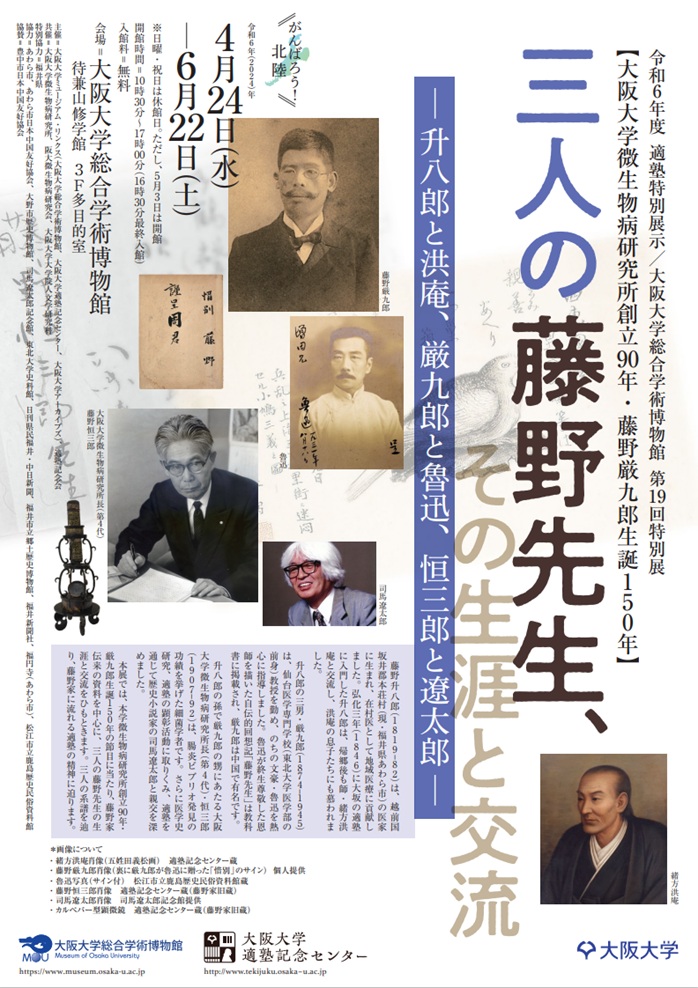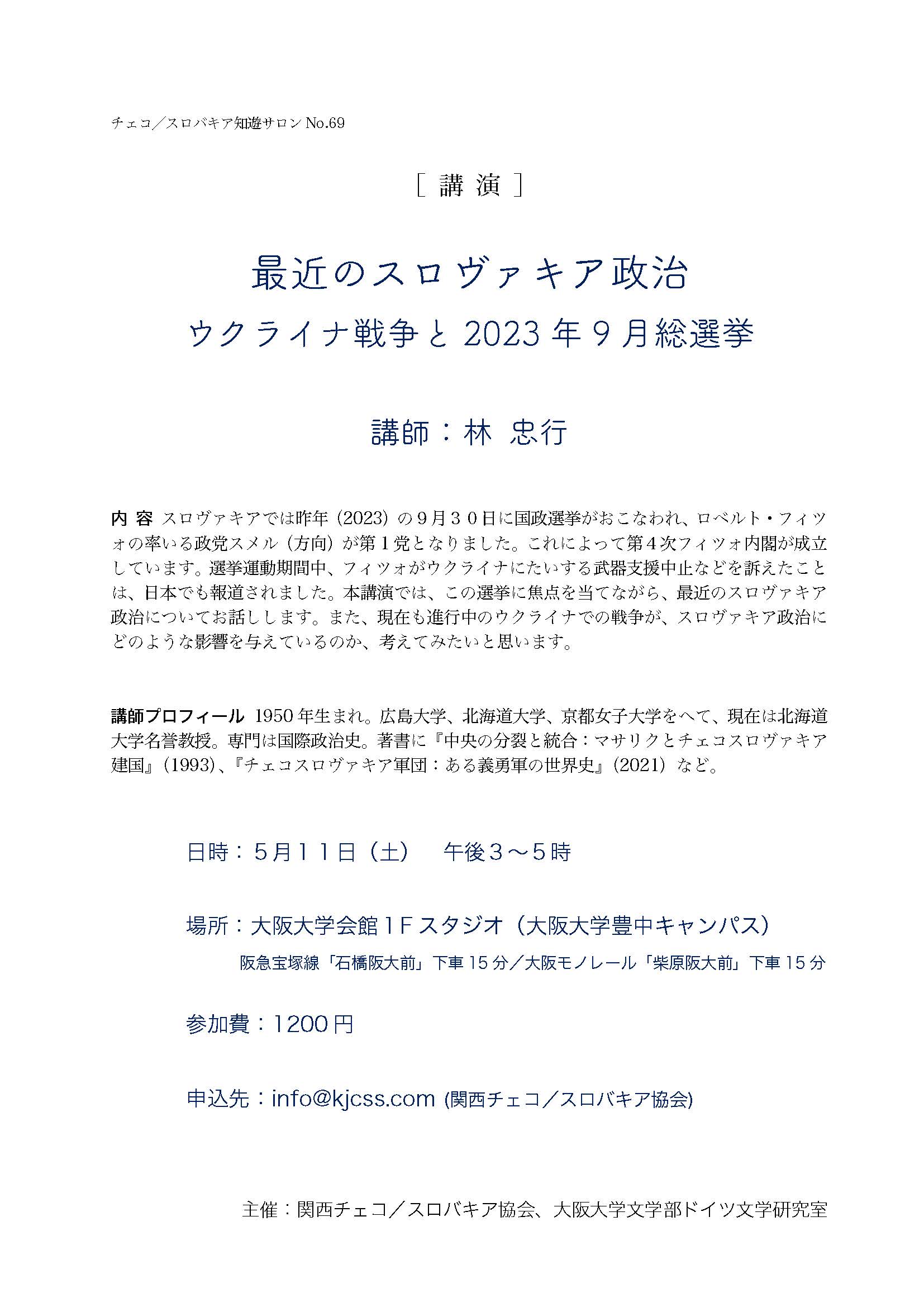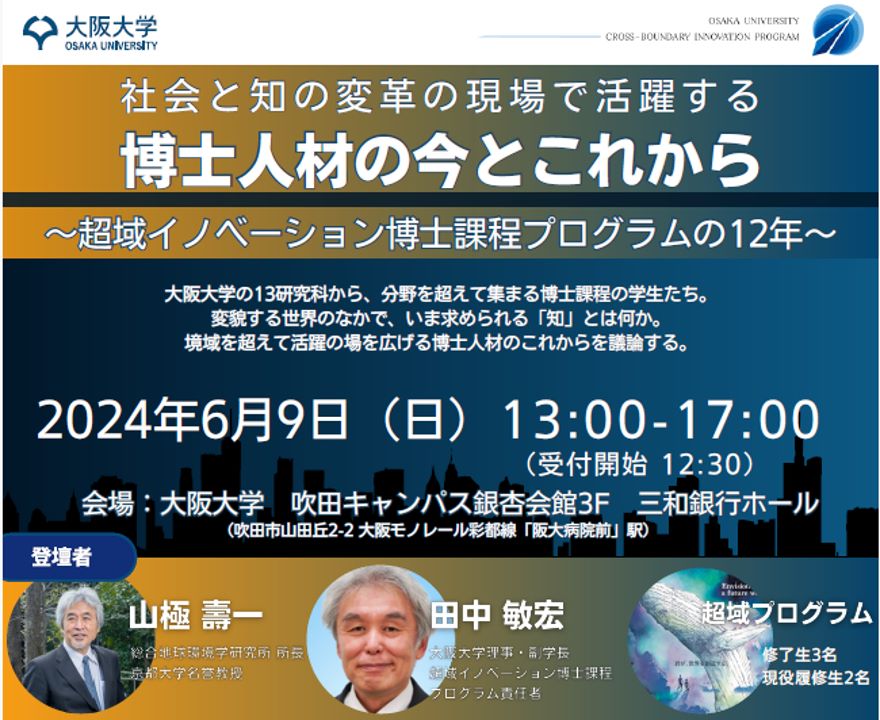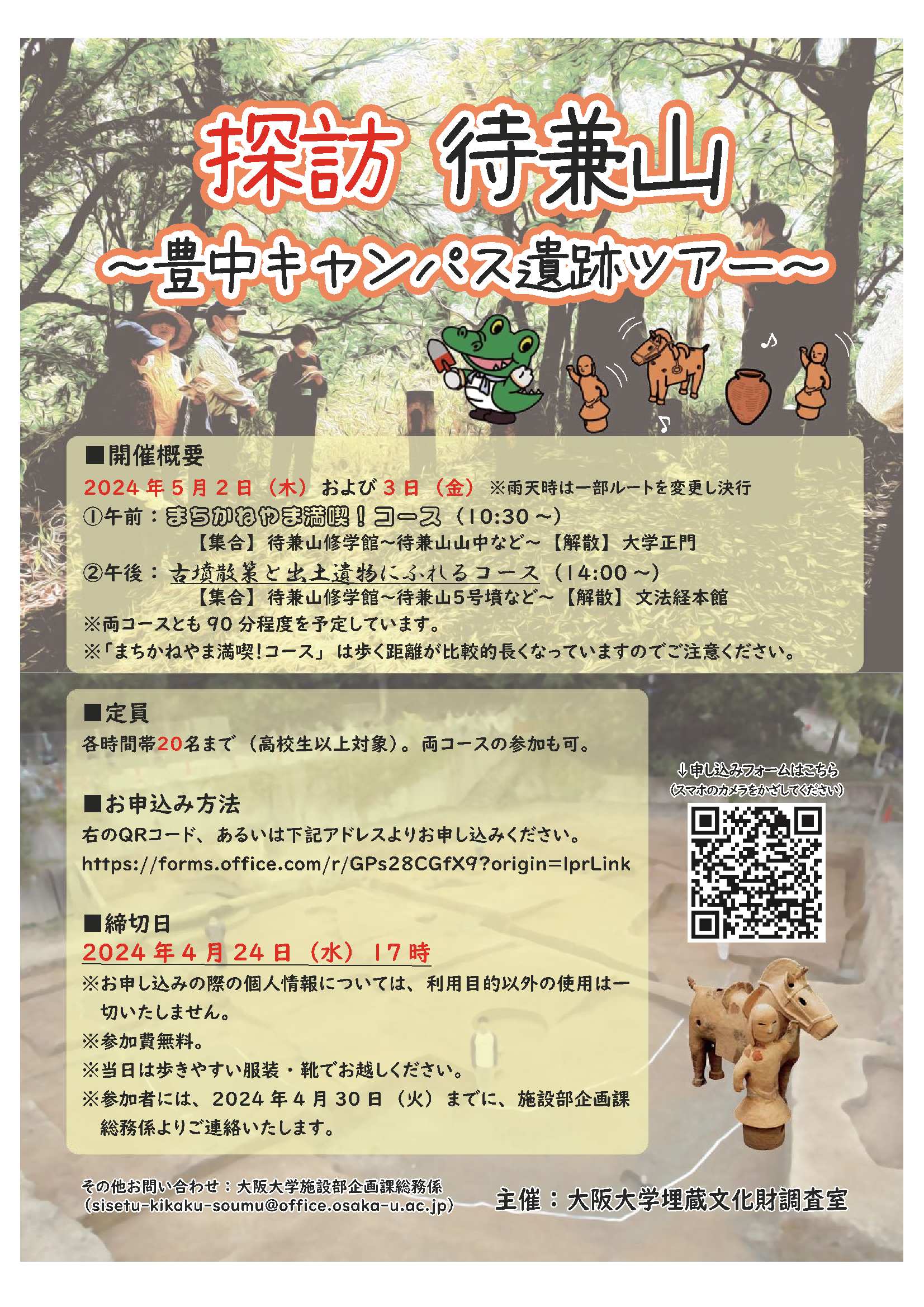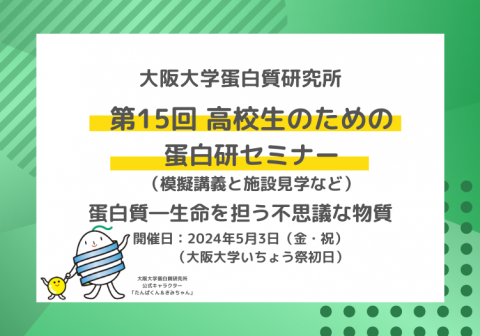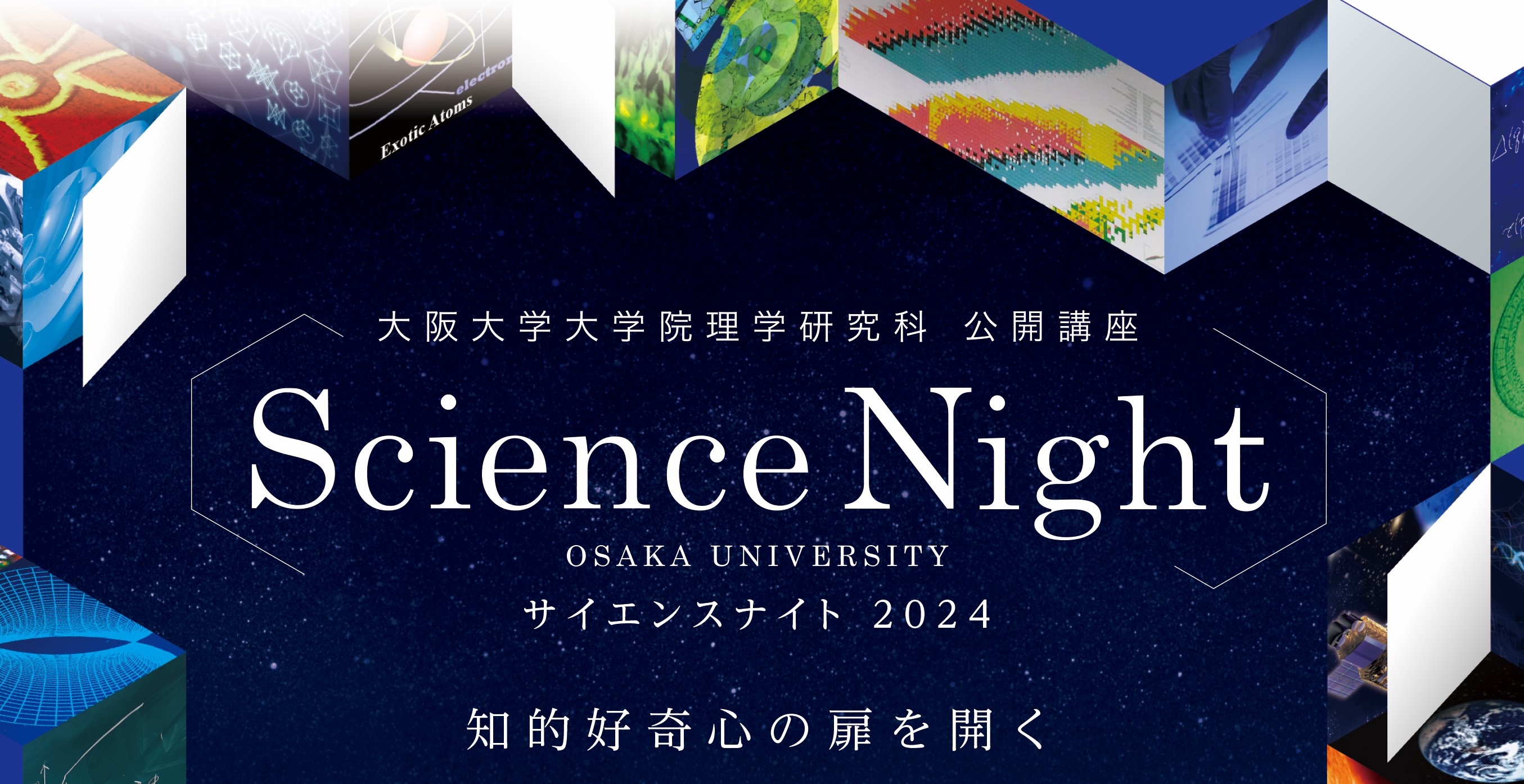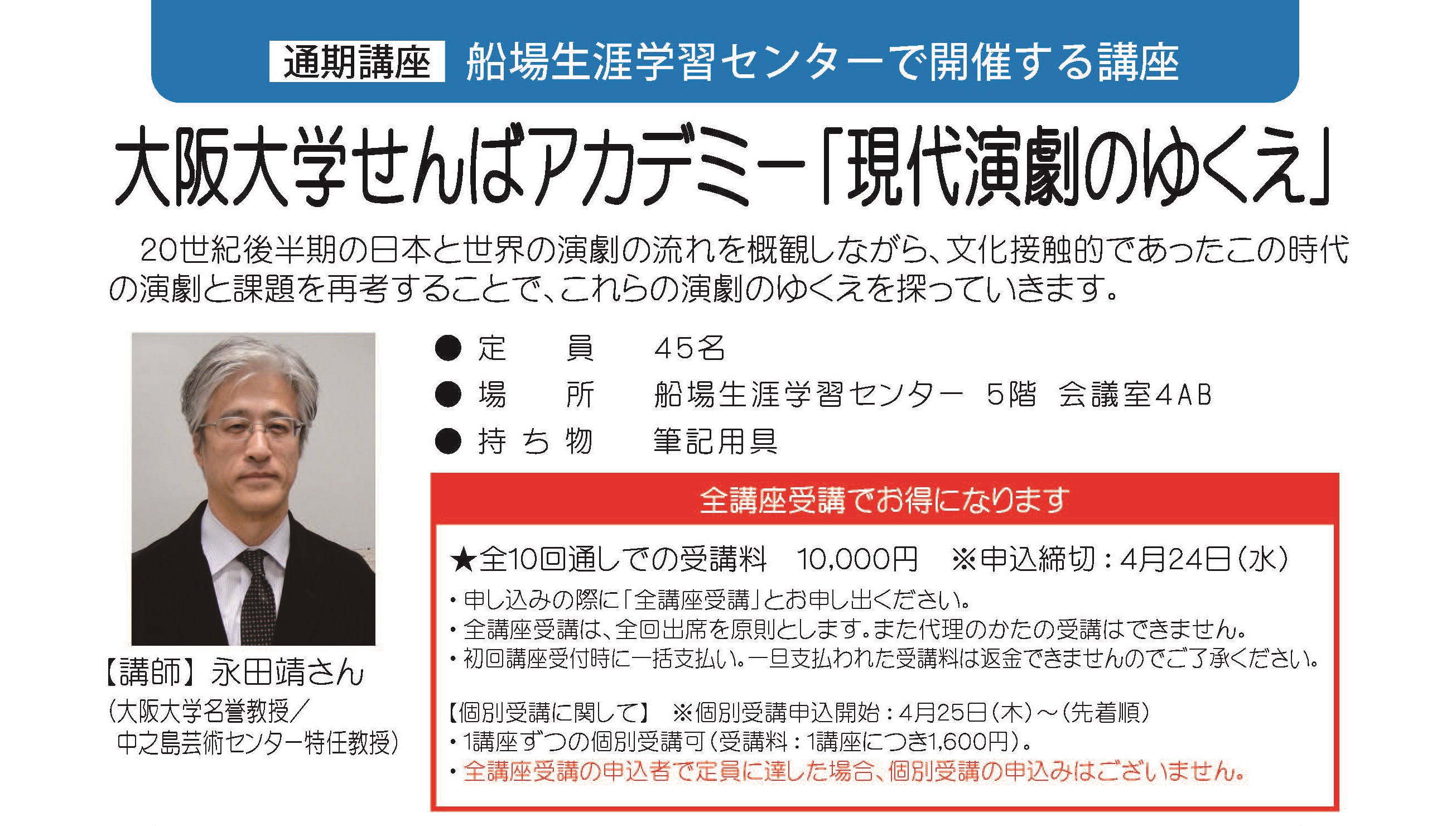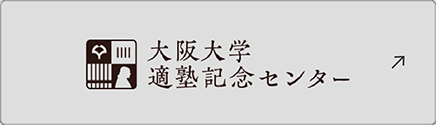社学共創の
実現を目指し、
21世紀懐徳堂は
歩み続けます。
「21世紀懐徳堂」は、大坂の商人たちが1724年に創設した学問所である「懐徳堂」の向学の気概を今の時代に伝え、つなぐために創設された知のネットワークの拠点です。
21世紀懐徳堂は、地域、社会及び市民と大学とを結ぶアウトリーチ活動を通じて、社会と共に学び社会と共に創る社学共創の輪を広げ、支援する役割を果たす組織です。
21世紀懐徳堂について知る
懐徳堂 2代目学主
中井竹山
©大阪大学大学院人文学研究科蔵
地図資料提供:古地図史料出版株式会社
注目のイベント情報
月別イベント一覧
月を選ぶ:

 メルマガ
メルマガ登録