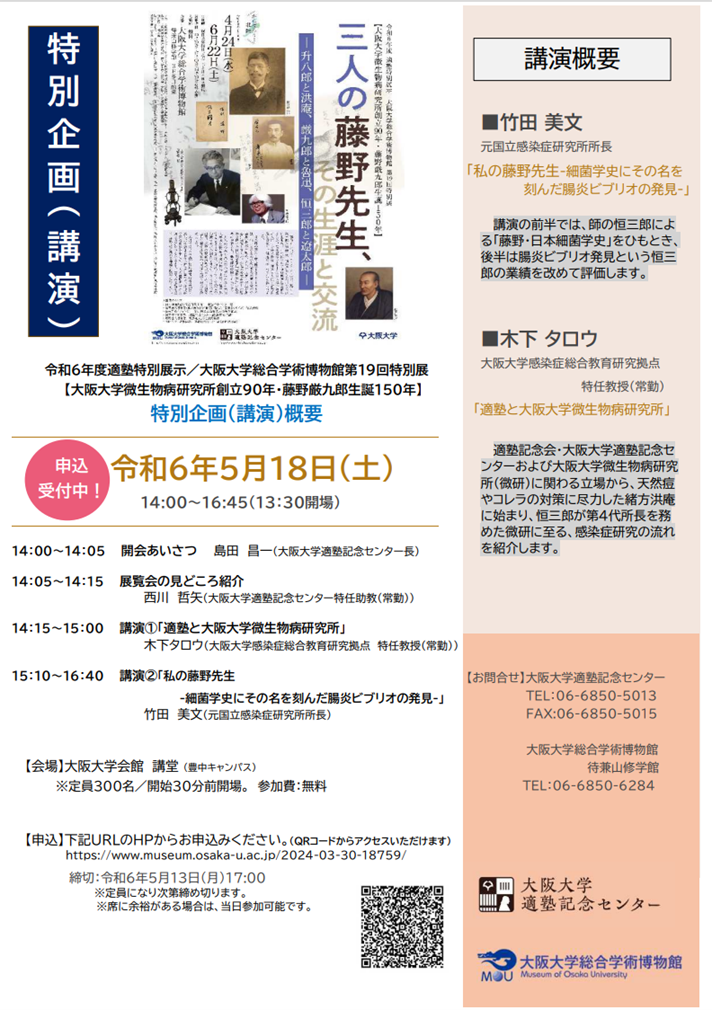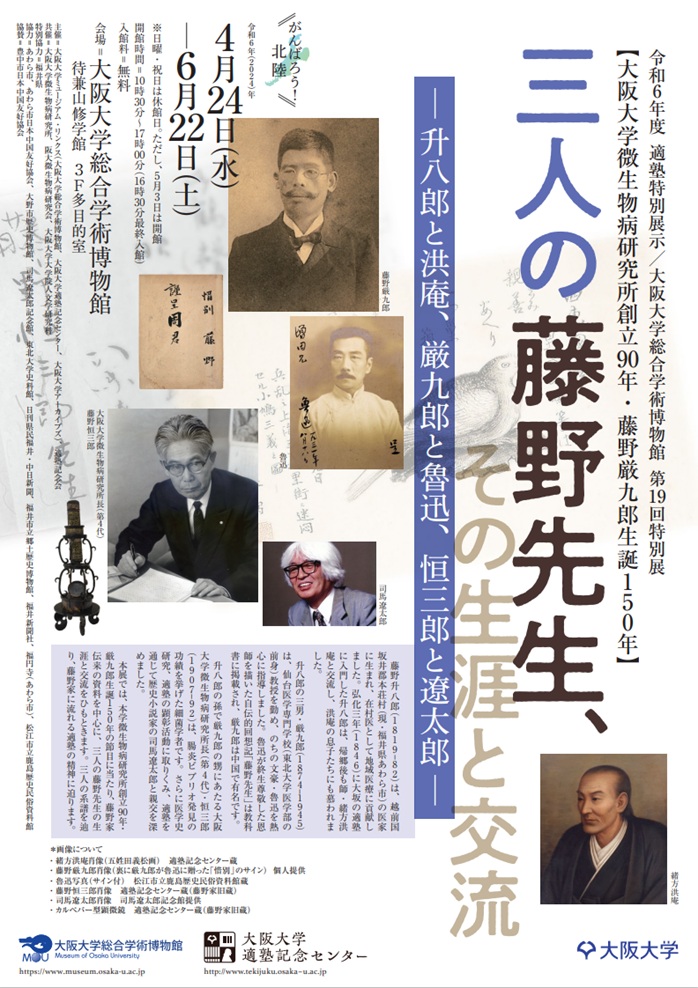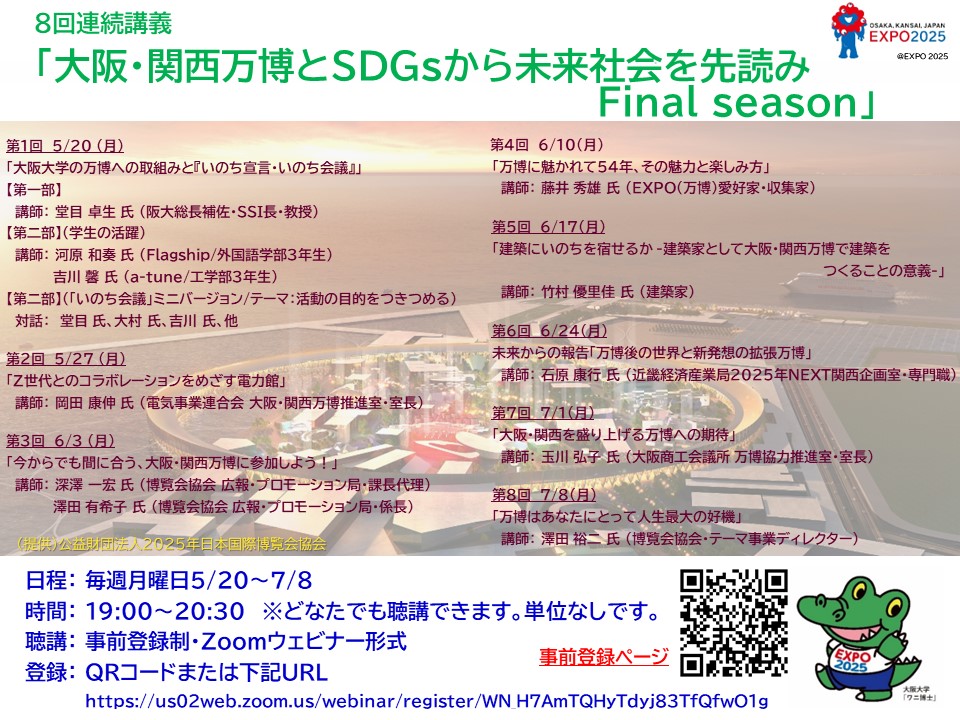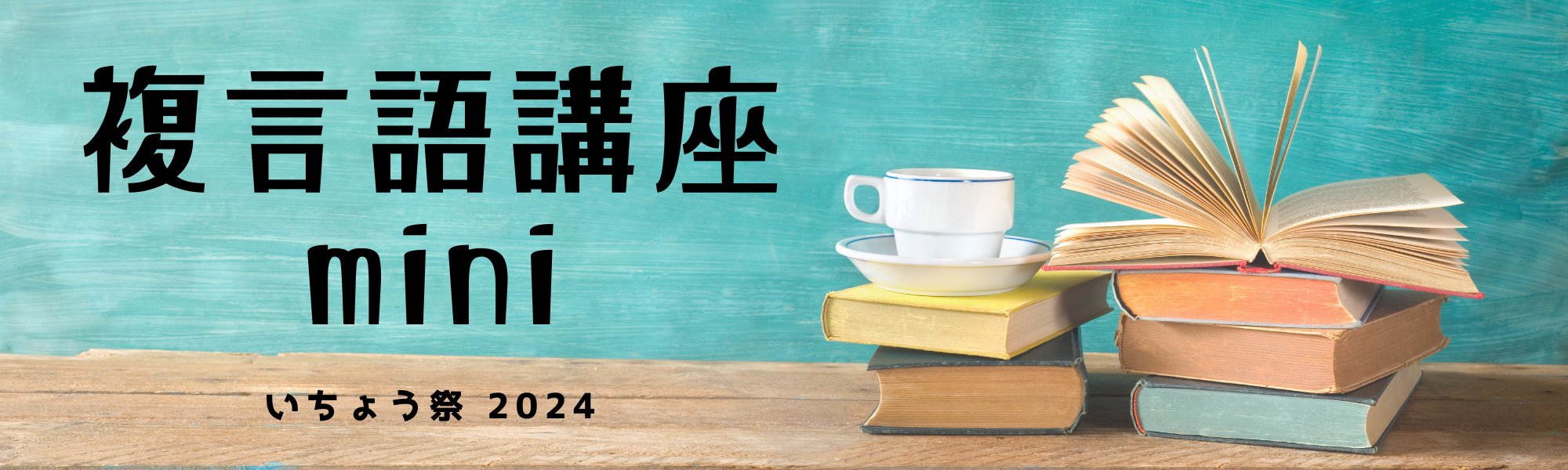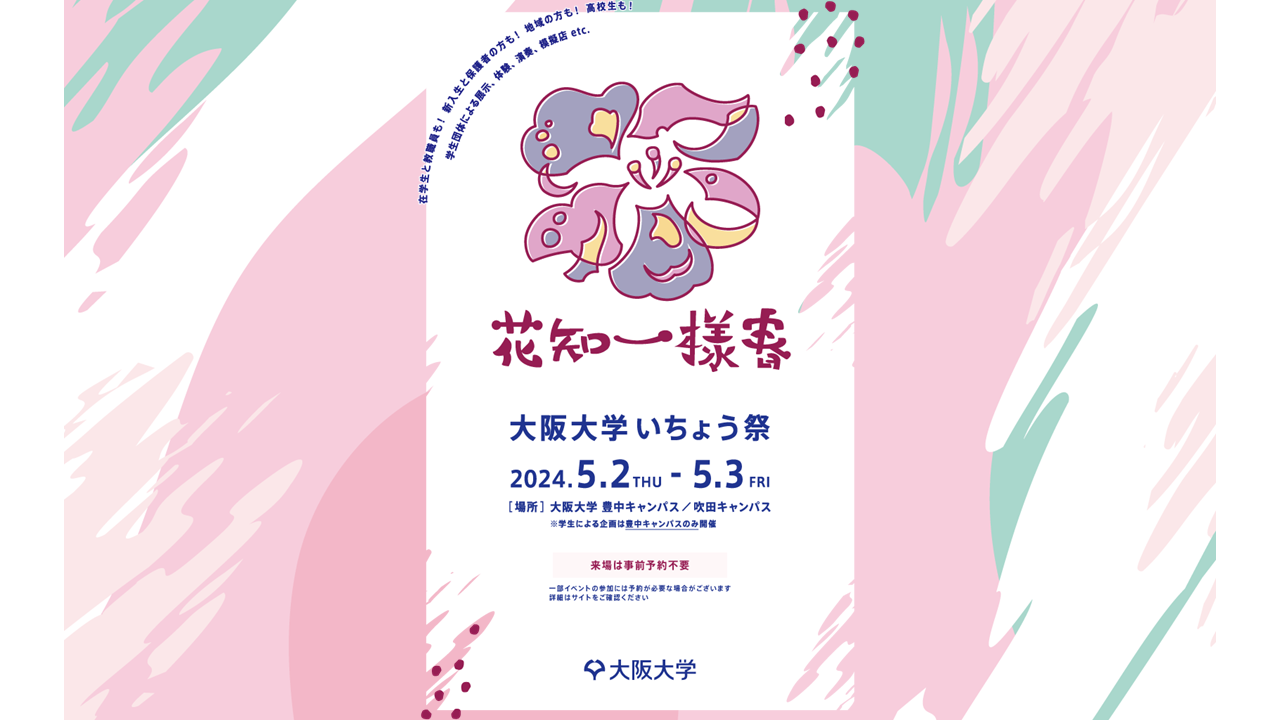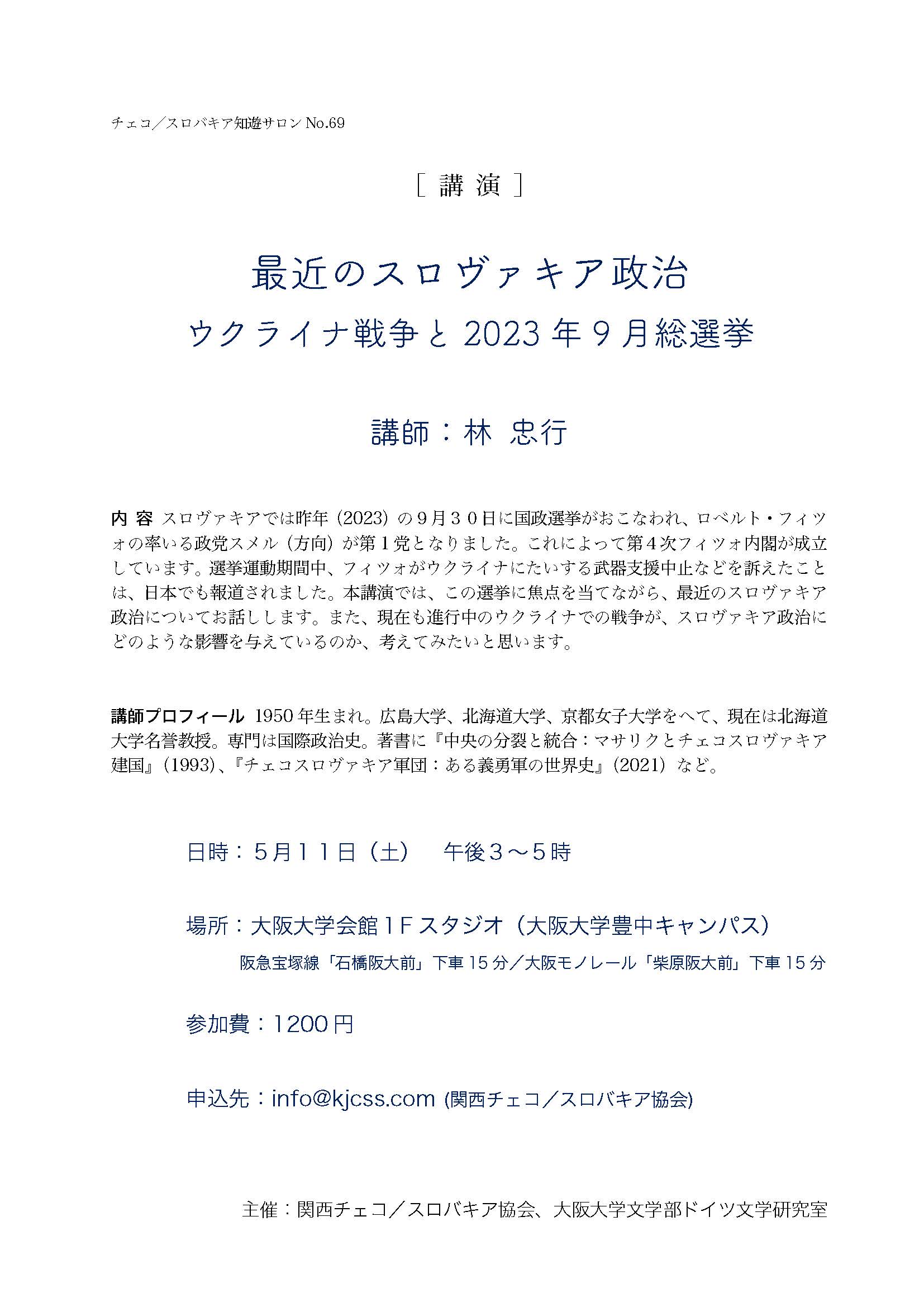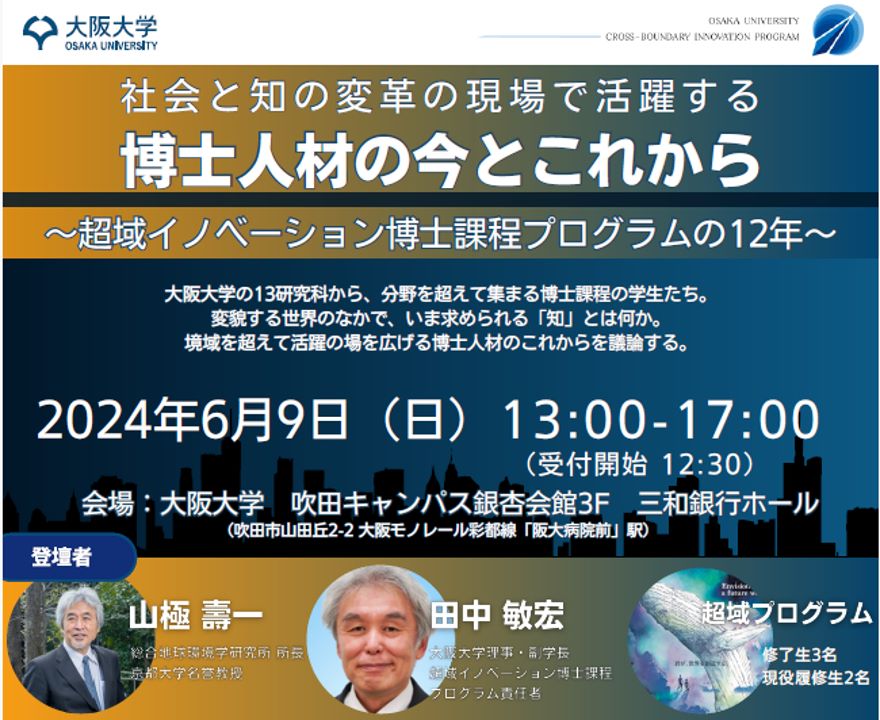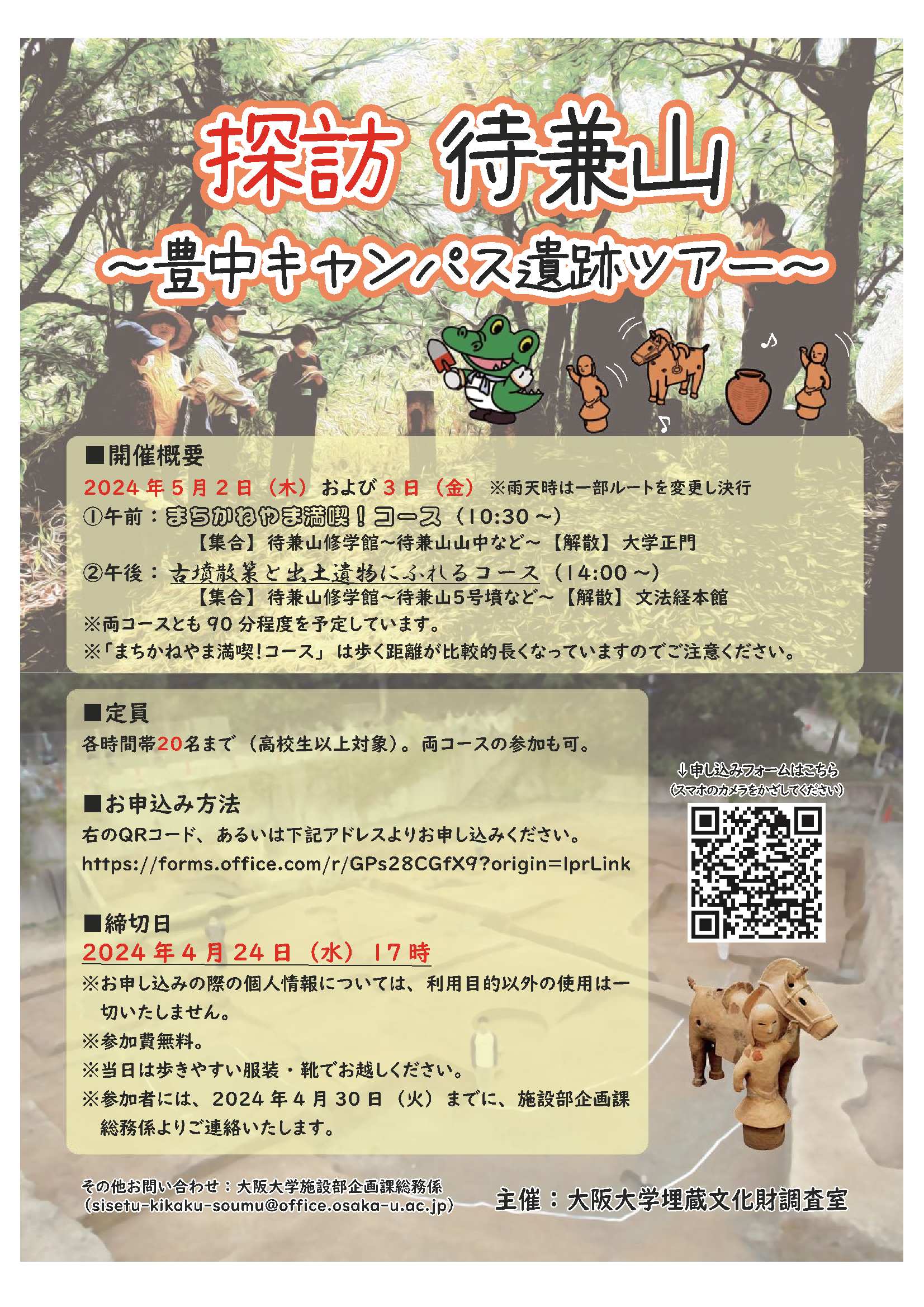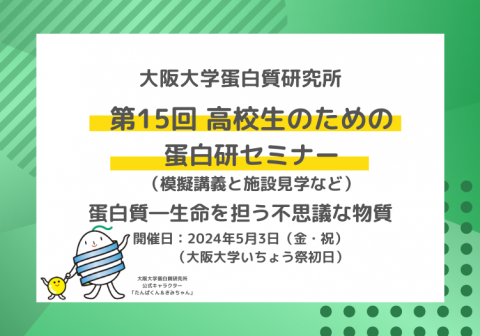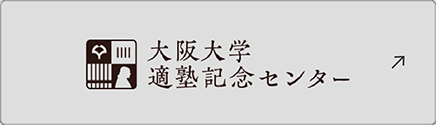社学共創の
実現を目指し、
21世紀懐徳堂は
歩み続けます。
「21世紀懐徳堂」は、大坂の商人たちが1724年に創設した学問所である「懐徳堂」の向学の気概を今の時代に伝え、つなぐために創設された知のネットワークの拠点です。
21世紀懐徳堂は、地域、社会及び市民と大学とを結ぶアウトリーチ活動を通じて、社会と共に学び社会と共に創る社学共創の輪を広げ、支援する役割を果たす組織です。
21世紀懐徳堂について知る
懐徳堂 2代目学主
中井竹山
©大阪大学大学院人文学研究科蔵
地図資料提供:古地図史料出版株式会社
注目のイベント情報
月別イベント一覧
月を選ぶ:
-
05/02(木)
受付中
2024 探訪 待兼山 ~豊中キャンパス遺跡ツアー~
-
05/02(木)
受付中
第5回阪大万博トークイベント「いのち会議・若者が描く未来社会3 ~紛争や分断のない未来社会はデザイン可能か?~」
-
05/02(木)
申し込み不要
「令和6年度 大阪大学いちょう祭」開催!
-
05/03(金)
受付終了
大阪大学ホームカミングデイ2024
-
05/03(金)
受付中
第15回 高校生のための蛋白研セミナー 蛋白質-生命を担う不思議な物質ー【5/3 (金・祝)開催:いちょう祭2日目】
-
05/03(金)
受付中
いちょう祭2024 複言語講座mini
-
05/11(土)
受付中
チェコ/スロバキア知遊サロン No.69 講演「最近のスロヴァキア政治 - ウクライナ戦争と2023年9月選挙」
-
05/15(水)
受付中
大阪大学大学院理学研究科公開講座 サイエンスナイト2024
-
05/18(土)
受付中
令和6年度適塾特別展示/大阪大学総合学術博物館第19回特別展 【大阪大学微生物病研究所創立90年・藤野厳九郎生誕150年】特別企画(講演)
-
05/20(月)
受付中
8回連続講義 「大阪・関西万博とSDGsから未来社会を先読み Final season」
さらに表示

 メルマガ
メルマガ登録